妖精が丘画廊 FAIRY HILL ART GALLERY フェアリーアート 妖精 絵本 妖精画 Märchen 水彩 ポストカード
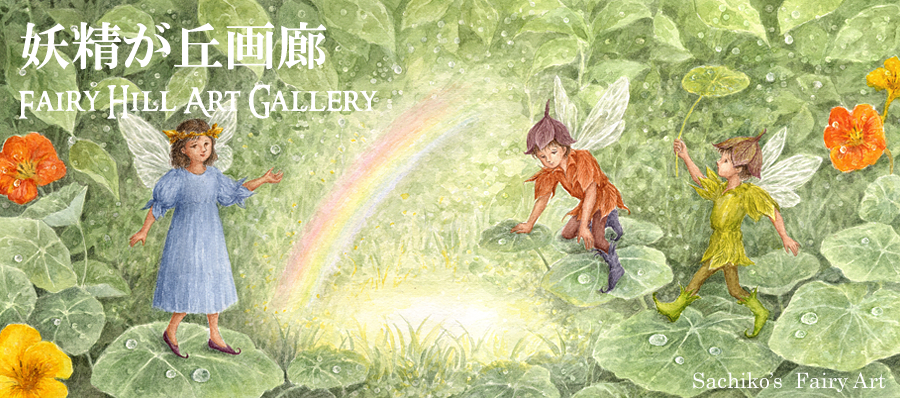
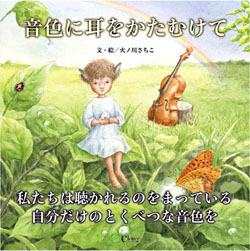

愛すべき妖精たち.....
外なる自然界と、わたしたちの内なる世界が、
鏡のように映しあうところ...
そのあわいに、彼らは棲んでいます。
物質でできたからだを持たず、肉体の目には見えないけれど、
彼らのはたらきなしには、花は彩られず、香らず、
そして、人間はほんとうの人間でいることができません。
人間は、彼らといのちをわかち合っているからです。
そうしてずっとずっとはるかな時をさかのぼっていくと
わたしたちは、同じ淵から生まれたのです。
すべてがひとつだった、あの源から.....
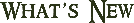
☆ブログ更新中です。
2025. 6.13 〈グリム童話の世界〉に「雪白と薔薇紅」を追加しました。
2025. 4.14 〈グリム童話の世界〉に「ガチョウ番の娘」を追加しました。
2025. 2.11 〈グリム童話の世界〉に「星の銀貨」を追加しました。
2024. 10. 9 〈ギャラリー1〉に「鬼の灯」を追加しました。
2024. 8. 1 〈グリム童話の世界〉に「赤ずきん」を追加しました。
2024. 5.27 〈ギャラリー1〉に「Lavender's blue」を追加しました。
2025. 6.13 〈グリム童話の世界〉に「雪白と薔薇紅」を追加しました。
2025. 4.14 〈グリム童話の世界〉に「ガチョウ番の娘」を追加しました。
2025. 2.11 〈グリム童話の世界〉に「星の銀貨」を追加しました。
2024. 10. 9 〈ギャラリー1〉に「鬼の灯」を追加しました。
2024. 8. 1 〈グリム童話の世界〉に「赤ずきん」を追加しました。
2024. 5.27 〈ギャラリー1〉に「Lavender's blue」を追加しました。


 Copyright (C) 2018-妖精が丘画廊 Sachiko Hinokawa All Rights Reserved. design by
Copyright (C) 2018-妖精が丘画廊 Sachiko Hinokawa All Rights Reserved. design by